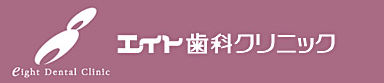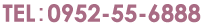認知症の第一人者が認知症になった
2020-01-13
 2020年1月11日に放送されたNHKスペシャルは、自ら認知症であるという重い事実を公表した認知症医療の第一人者 長谷川和夫先生(90)を取り上げていました。
2020年1月11日に放送されたNHKスペシャルは、自ら認知症であるという重い事実を公表した認知症医療の第一人者 長谷川和夫先生(90)を取り上げていました。「長谷川式」と呼ばれる早期診断の検査指標を開発、「痴呆」という呼称を「認知症」に変えるなど、人生を認知症医療に捧げてきた長谷川先生とその家族の姿をNHKはこの1年記録し続けてきました。
認知症専門医が認知症になったという現実をどう受け入れ、何に気づくのか。人生100年時代を迎え、誰もが認知症になりうる時代。長谷川先生が気づいた新たなメッセージを届け、認知症新時代を生き抜くための「手がかり」と「希望」を紡ぐ番組でした。
 日経Gooday2020年1月特集には、国立長寿医療研究センターの遠藤英俊先生が、最新の研究結果を基に認知症予防について解説していました。
日経Gooday2020年1月特集には、国立長寿医療研究センターの遠藤英俊先生が、最新の研究結果を基に認知症予防について解説していました。手軽でありながら、認知症予防に効果が期待できる娯楽としてカラオケが挙げられていました。
カラオケは何よりストレス発散になります。不安で落ち込んだ気分を解消することは、認知症のリスク要因を減らすことにもつながります。
国立長寿医療研究センターで行っているピアノに合わせて歌うなどの音楽療法は、認知症に伴って現れる多動、徘徊、不安・焦燥、アパシー(無気力状態)などの行動・心理症状(BPSD)の改善に有効だったそうです。
また、声を出すことで喉の機能が鍛えられるため、誤嚥防止にも効果があります。
誤嚥性肺炎を防ぐことが健康長寿につながることはいうまでもありません。
 年齢を重ねてくると、最近のことは忘れても、昔のことは鮮明に覚えているという場面が増えてきます。しかし、昔を思い出すことは、決して後ろ向きの行為ではありません。
年齢を重ねてくると、最近のことは忘れても、昔のことは鮮明に覚えているという場面が増えてきます。しかし、昔を思い出すことは、決して後ろ向きの行為ではありません。
過去を振り返ることは、忘れかけていた記憶を想起させ、脳の「前頭前野」を活性化する働きがあります。
そうした考えのもと、懐かしい写真や生活用具などを使い、過去に思いをめぐらすことで、現在そして未来に目標や夢を持とうと開発された心理療法が「回想法」です。
カラオケ、麻雀、昔話といった意外なモノが認知症予防につながるとしたら、活用しない手はありません。
配信 Willmake143
←「冬の室内、乾燥を防ぐ」前の記事へ 次の記事へ「がんでも食べられる」→